ワンオペ育児とは?つらいワンオペ育児と家事の乗り切り方

子育てをしていると「ワンオペ育児」という言葉をよく耳にします。共働き家族が増え、日々の働き方も見直されている昨今ですが、それでもワンオペ育児をしているという家庭は多いのではないでしょうか。「ワンオペ育児」という言葉の意味、そして「ワンオペ育児」で家事や子育てに追われている皆さんの実際の乗り越え方法などをご紹介します。
ワンオペ育児ってどんな意味?
ワンオペとは、「ワンオペレーション」の略。担い手が1人しかいない状態のことを指します。ファーストフード店やコンビニエンスストアなどで、過酷な労働環境を表す言葉として使われていました。
その後、「ワンオペ育児」という言葉がSNSなどで使われ始めました。こちらは、ひとりで育児と家事などの大半をこなさなければならない状態を指しています。2017年には流行語として、「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされています。主に、家族の責任を一人で背負わなくてはならない孤独感や辛さを表す言葉として使われています。

ワンオペ育児を担うのは誰?
2016年社会生活基本調査(総務省)によると、6歳未満の子どもをもつ夫(夫婦と子どものみの世帯に限る)の1日当たりの家族育児時間は1時間23分、妻は7時間34分です。
表4-2 末子の年齢階級別夫・妻の家事関連時間の推移(平成8年,28年)-週全体,夫婦と子供の世帯 (平成28年社会生活基本調査より)
この数字を見ても、妻の方が圧倒的に家事や育児時間が多いことがわかります。

平成8年の調査では、夫の家事育児時間は38分だったので、それに比べては増加しているものの、変わらず妻の負担が大きいです。ちなみに、平成8年では、妻の家事育児時間は7時間38分でしたので、あまり変化はありません。
ワンオペ育児をしていると感じている人はどのくらい?
ポピンズシッターをご利用いただいている方にもワンオペ育児に関するアンケートをさせていただきました*。『自分は「ワンオペ育児」をしていると感じたことはあるか』という問いに対し、72.5%のかたが「はい」と答えました。多くの方が「ワンオペ育児」をしていると感じているようです。
ちなみに、102名の回答者のうち、約91%は「ママ」からの回答でした。

皆さんがワンオペ育児をしていると感じる理由として「パートナーの帰りが遅い」、「パートナーが単身赴任中」、「シングル家族」といった回答を多くいただきました。アンケートにご協力いただいた皆さんの回答も一緒にご紹介しましょう。

夫の会社や夫が育児をする前提で働いてくれない。無理解
(2歳のママ)

育休中の今、長女は短時間保育なので7:20起床21:00就寝でパパにまったく会わない。“今日も帰って来なかったね”と言っているくらい。家事育児全て自分。
(0歳のママ)
男性の労働時間が長いことが、ワンオペ育児の要因の一つだと言われています。早朝に家を出て、帰宅時間が深夜になるという家族も多いようで、アンケートでもこういった回答をたくさんいただきました。

2020年の男性の育休取得率は12.65%です。過去最高の数字とはいうものの、まだまだ低い状況が続いています。男性が子育てに参加しやすい環境が増えれば、男性の意識も変わってワンオペ育児の状況も改善されてくるのでしょうか。
ワンオペ育児をしている0歳のママからは、子どもたちの体調や行事、家事なども全て一人で把握しているので、気を緩めるタイミングがないとの声もありました。
【ワンオペ育児の理由】パートナーが単身赴任中、シングル家族

夫が海外に単身赴任して実家も遠方だったので
(2歳のママ)

未婚なので完全にワンオペ
(1歳のママ)
アンケートでは、ワンオペ育児の乗り越え方についてもお伺いしました。
ひとり親家庭だという方からは「子どもが健康で無事であればその日はオッケーとする」と回答をいただきました。その他、「無理しすぎないこと」「シッターさんに頼みました。本当に救われました」といった回答もありました。
頼れる人が近くにいない状態でのワンオペ育児は、保護者が精神的に追い詰められる状況にもなりかねません。自治体の助成などを利用し、時には自分が育児や家事から離れることも大切です。
自分はワンオペ育児ではないと感じているのはどんな人?
一方で『自分は「ワンオペ育児」をしていると感じたことはあるか』という問いに対し、27.5%の方が「いいえ」と回答しました。「いいえ」と感じる理由はこちら

夫も均等に家事・育児を担当しているため
(6歳と2歳のママ)

夫が家事育児の大変さに理解があるため
(0歳のママ)

シッターさん、夫、実母、ご近所さんに家族の情報を常にオープンにし、助けてもらう
(6歳と3歳のママ)
などがありました。中でも、「パートナーと完全協力でやっている」という回答が多くみられました。ワンオペ育児を脱するには、自分以外の誰かの協力が不可欠です。
先輩ママに聞きました!ワンオペ育児の乗り越え方
アンケートでは、ワンオペ育児を乗り越えるコツについてもお伺いしております。回答の中には、「子供のかわいさで癒されながらひたすら耐える」「気合い」など歯を食いしばって乗り越えようとするものや、「今の成長は今しかみられないと楽しむように気持ちを高めている」といった意識を変えるように心がけるといったものもありました。
とはいえ、精神論で乗り切るには、その状態が長引けば限界がくることがあるかもしれません。その他、皆さんの乗り越え方をご紹介しましょう。
家事の手を抜く

優先順位を考える。重要度の低い家事を後回しにする
(6歳と0歳のママ)

家事は家電に任せる。食事は作らない
(5歳のママ)

家事を簡略化、外注する
(0歳のママ)
家事を外注するのも良い手段。料理や掃除、洗濯などをサポートしてくれる「家事代行サービス」を使うことを後ろめたく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、頼むことでストレスから解放されたという声も多いようです。
ポピンズシッターの「かんたん家事」
ポピンズシッターでは、保育時間の前後にかんたん家事のサービスを実施しております。ちょっと手が足りない。。。そんな保護者さまの日常の家事をお手伝いします。例えば、掃除機かけや、お風呂やトイレのお掃除、洗濯、離乳食作りなどにも対応。
<かんたん家事とは>
保育時間の前後に、家事を最短30分からお願いできます。例:保育2時間 + 家事30分*日常的な家事をお手伝いします。
*家事の時間では、お子さまの保育はできません
*家事のみのご依頼はできません。<料金>1,650円/1時間(税込)*30分~ご依頼できます
*家事の依頼時間分は、保育料はかかりません例:
保育2時間、家事1時間の依頼保育 15時~17時(2時間) 2,200×2=4,400円
家事 17時~18時(1時間) 1,650×1=1,650円
総額(税込) 6,050円
※時給2,200円のシッターの場合
※上記は2025年3月31日までの料金です
ご依頼・詳細はこちら
夫にも家事や育児に参加してもらう

ワンオペ育児は正直、かなり体力的にも精神的にも辛い時期でした。私の場合は、夫に相談したところ、夫が朝方の仕事に転職してくれたのでどうにかなりましたが、それが無理な環境であれば、絶対に両親や親戚、近隣の友人、区のファミリーサポートの方やシッターさんなどに頼るのが良いと思います。
(5歳のママ)

休みに旦那に任せる日をつくる、シッターさんに頼む日をつくる。
(7歳と5歳のママ)
まずは、パートナーにどれだけ負担が偏っているかを理解してもらうことが大切とのこと。一方で、解決方法として「夫に期待しない」という回答も多くありました。その場合、他の手段で頼れる人を見つけておくのも良いでしょう。他の人の助けではどんなものを利用できるかについては、「シッターなど他の人に助けてもらう」で解説します。
話を聞いてもらう

Twitterで育児アカウントをつくりママ友とやり取りをする
(6歳と1歳のママ)
「カフェで一息。お友達と会って話す」や、「愚痴を吐くのが大事」という声も多数ありました。その他、地域にある「子育て支援センター」に行って相談をしてみるのも良いでしょう。子育て支援センターでは、子育てで孤立化しないために、親子が気軽に集える場を提供しています。地域の子育て経験者が家庭訪問をしてくれる「訪問育児サポーター」、「子育てひろば」、全国で自主的に行われている「ママサークル」なども利用してみるのも良いでしょう。
ベビーシッターなど人の手を借りる!

友人、会社の同僚に泊まりに来てもらって助けてもらう。保育園、シッターさんにお世話になりまくる。社会に育ててもらう。
(4歳のママ)

信頼できるシッターさんをみつけ、自治体から助成の範囲で有効に使いたい。
(3歳のママ)

ベビーシッターを利用する、子供と2人だけになりすぎないよう適度に出かける。
(0歳のママ)
アンケート回答の中には、ワンオペ育児を乗り切る方法として「ベビーシッターを利用する」という声をたくさんいただきました。そして、シッターを利用することが「気晴らしになった」という声もありました。
自分が健やかに子どもと過ごすためにも、「他の人に助けてもらう」という方法も検討の価値があるのではないでしょうか。
ちなみに、ベビーシッターの助成制度には、東京都にお住まいの方であれば東京都「ベビーシッター利用支援事業」というものがあります。一時保育でも使える場合も。詳しくはこちらをご覧ください。
子どもを一時的に預ける場としては、ベビーシッターの他にも下記のような手段があります。
・保育園や幼稚園、認定子ども園での一時預かり
・ファミリーサポート
・ショートステイやトワイライトステイ
・放課後児童クラブ
育児の悩みを一人で抱え込まず、ぜひ利用してみてください。
*アンケート概要
「子育てと仕事の両立」に関するアンケート
2021年10月13日~17日。ポピンズシッターご利用者様にインターネットによるアンケート。回答数102。

ポピンズシッター 【公式】
「仕事と育児の両立」のその他の記事を見る
-
一時保育とは?利用方法・メリット・一時保育が利用できない場合の預け先
兄弟の行事・美容院・育児疲れ・冠婚葬祭などで一時的にお子さまを預けたいときには、自治体の「一時保育」 […]ポピンズシッター 【公式】
-
今回インタビューにご協力してくださったのは、フルタイムのシフト勤務で施設管理や従業員管理のお仕事をさ […]
ポピンズシッター 【公式】
-
着替えない!行きたくない!間に合わない!幼稚園・保育園への送迎ハプニング、先輩ママの対処法とは
保育園や幼稚園の送り迎えには、ハプニングがつきものです。園の送りでギャン泣きされたり、お子様の対応に […]ポピンズシッター 【公式】
![[ポピンズシッター]poppins sitter](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/production-penguin-web-assets/assets/top_v1_2/logo_smartsitter-e883a774646de00d9dc586599b6c6aea6e96fa1327ab8745010f386c4e0fa6d4.png)



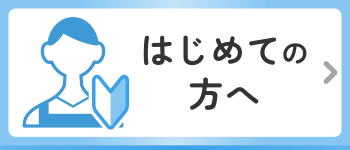

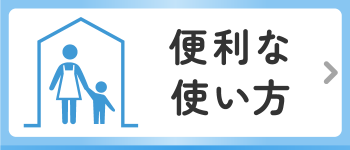
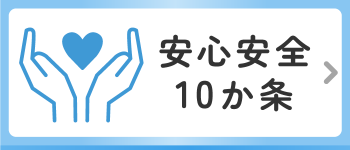
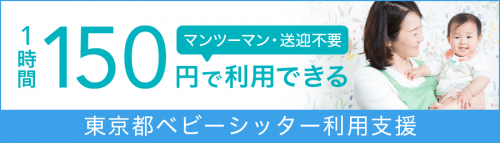


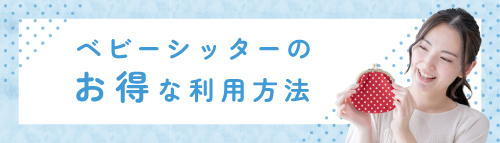
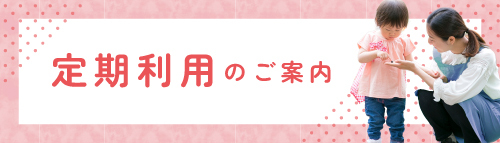
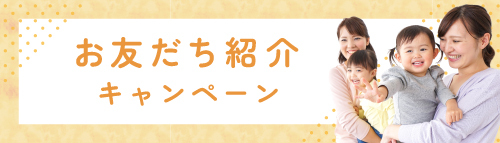


【ワンオペ育児の理由】パートナーの帰りが遅い
パパは週6勤務、かつ子どもが寝た後でないと帰ってこられない
(5歳のママ)