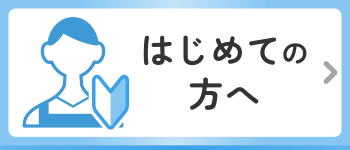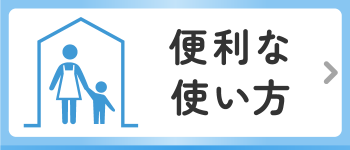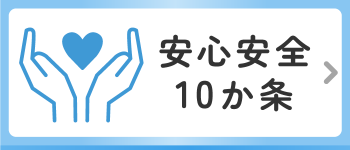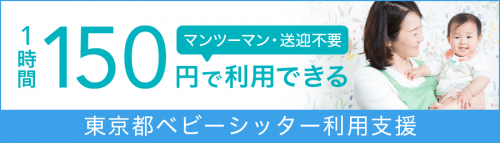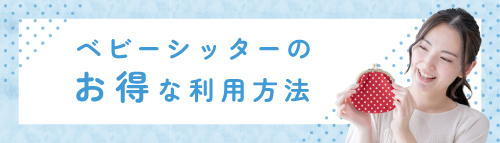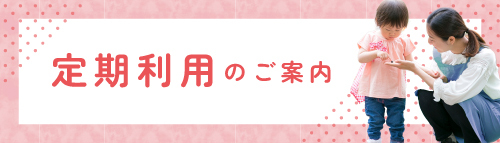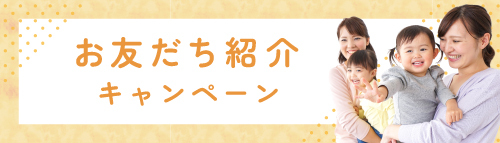申し込みはいつからスタート?働くママパパのための学童講座

お子さまが小学生になると、共働き家庭に必要になる「学童」。
学童は保育園の延長と思いがちですが、申し込み方や施設の形態によって、保育料や保育時間などにバラつきがあり、色々疑問点が出てくるもの。
- 学童の申し込みはいつから?
- 何を基準に学童を選べばいいかわからない
そんな疑問にお答えします。
学童ってどんなもの?
まずは学童について、具体的に知っておきましょう。
学童はどんな場所?
学童は「放課後児童クラブ」のことです。正式名称は「放課後児童健全育成事業」と言い、厚生労働省が管轄し児童福祉法や社会福祉法によって運営されています。
主に、小学生の保護者さまが仕事や介護、病気などで放課後にお子さまを保育できない場合、代わりにお子さまを預かって保育してくれる場所です。放課後や夏休みなどの長期休暇に、お子さまが安心して過ごせる場所を提供してくれる施設で、児童の健全な育成を目的としています。
全国に26,000ヶ所以上あり、130万人ほどのお子さまが登録しています。登録者は増加傾向です。
放課後児童健全育成事業について
(厚生労働省ホームページより)
学童では以下の活動を行い、指導員に見守られて過ごします。
- 下校後自分たちで学童へ移動
- おやつの時間
- 宿題の時間
- 自由遊び(室内、戸外遊び等)
- お迎えを待つ・自分たちで帰宅する
友だちや上級生(下級生)と関わる学童は、生活を共にする中で社会性が身につく側面もあり、お子さまにとって貴重な体験の場になるでしょう。
また、学童には民間学童と自治体が運営する公設学童(公設公営、公設民営)があります。それぞれ受けられるサービスや、保育時間に違いがあります。
民間学童とは?
民間企業が設置・運営している学童があります。全国にある学童の7割前後が民間の学童です。
法人によって内容や理念がさまざまですが、たとえば以下のようなオプションサービスもあるのが特徴です。
- 習い事の送迎をしてくれる
- 習い事の場の提供
- 学習塾的機能との併用
- 早朝、夜間保育の実施
- 夕食の提供
- 自宅までの送迎サービス
- 利用条件が緩く利用しやすい
- 保育料は公設に比べて高め
オプションのサービスは保育料に上乗せされるため、公設学童に比べると保育料が高くなります。しかし、忙しい保護者さまにはかゆいところに手が届くサービスが充実しており、満足度も高いでしょう。

しかし、デメリットは比較的最近設置されたところが多く、敷地が狭い、外遊びできない、ビル内にある、不便な場所にある、といったケースもあるようです。
公設学童とは?
公設学童は「公設公営」と「公設民営」に分けられ、自治体運営、委託しています。
公設公営は、自治体が設置・運営しており、公設民営は自治体が設置、運営は民間企業やNPO法人、保護者会などが運営しています。「公立」的な位置付けで昔から運営しているところが多く、保育料もリーズナブルな傾向があります。
しかし、保育時間は民間に比べると短めで、オプションサービスも少ないのが難点。
昔から設置されているため、小学校の敷地内や近隣に設置され、好立地な場所にあります。学校からの移動の負担が少なく、学校の校庭で遊ぶことができる学童もあり、お子さまにはメリットが感じられるでしょう。
学童の保育時間は?
学童の保育時間は、
学校がある日で概ね
- 民間学童:〜20時・〜21時ごろまで
- 公設学童:〜18時半・〜19時まで
学校がお休み・長期休暇のは
- 民間学童:6時半〜21時(日祝も開所しているところがある)
- 公設学童:7時〜19時(日祝は基本的にお休み)
祝祭日や学校がお休みの日、夏休みなどの長期休暇の日は基本的に1日開所しています。上記はあくまでも目安なので、各自治体や法人に確認してみるとよいでしょう。
学童の利用料金は?
公設学童の保育料相場は、4000~6000円のところが最も多いようです。保育園と違い、所得による金額の差はないことがほとんどです(※施設によります)。
民間学童の保育料は、企業や法人によってばらつきがありますが、概ね月額30,000円から50,000円です。
民間、公設関係なく、一般的に早朝や夜間は延長保育料や捕食・食事代が別途かかります。目安としては、〜7時、18時以降に延長料金がかかる傾向があるため確認しておきましょう。
申し込み準備はいつからスタート?入所までのスケジュール
学童はお子さまが年長さんのうちから探し、申し込みをする必要があります。「明日から入所したいです」と飛び込みで入れるわけではなく、とくに公的学童は就業の状態などの書類提出などを行って入所決定される施設です。
申し込み準備のスケジュール
春〜夏前:通えるエリアの学童を調べる
まずは、お子さまが自分の足で通える範囲の学童を探しましょう。いくつかピックアップし、条件に合うところを調べておきます。インターネットの口コミや実際通わせている方の話は重要な情報なので、できるだけリサーチしましょう。

また、防犯や事故防止を考えると、小学校や自宅からなるべく近いところが安心です。お子さまの足で通えないようでしたら毎日の利用は難しいかもしれません。
初夏〜夏休み・夏祭りに参加したり見学をする
7月には七夕、夏休み中は夏祭りなどを開催している学童が多いため、可能であれば参加させてもらいましょう。年長さんを対象に、地域の掲示板やホームページで呼びかけていることがあります。学童のお子さまや指導員の様子をみるチャンスです。
秋〜冬前・就学時検診で情報収集し説明会日時を把握する
小学校では、毎年秋から冬前にかけて「就学前検診」があります。そこで学童のパンフレットや、説明会日時が記載された書類を配布されることが多いので、必ず受け取るようにしましょう。
もちろんパンフレット等をもらえないこともあります。その場合は、直接学童に電話で来年度の入所希望の旨を伝え、説明会がないかを問い合わせてみましょう。
冬休み前後・入所説明会に参加する
いよいよ入所説明会の時期。施設内をみることができるのはもちろん、指導員に直接質問できるチャンスでもあります。ぜひ参加してください。
複数の学童で迷われている方は、本命や希望順をお子様と一緒に考え結論を出します。
2月頃・入所手続き
希望する学童へ入所手続きを行います。施設によって異なりますが、「就学前検診の時に渡された、学童の書類に同封された申し込み用紙に記載して提出する」がポピュラーです。
先着順で決まる場合もあれば、定員を超えている時は状況を考慮し、調整されることもあります。特に駅近やマンモス校の近く、利便性の高い学童は希望者が多い傾向があります。噂は鵜呑みにせず、入所決定通知が届くまでは、入所できなかった時の対策を考えておきましょう。
3月上旬・入所決定、手続きと面談
3月に入所決定通知が届き、入所決定者向けの説明会があります。その後指導員との面談や手続きもあり、忙しい時期です。
入所決定者向けの説明会では、保育料の支払いについてや持ち物などの案内があります。また、入学前の3月中(春休み)から保育を受け付けている学童では、春休みの対応を聞くことができるでしょう。
一般的には新年度の4月1日から学童生活が始まります。しかし、学童によっては保育園や幼稚園卒園後、3月中から「プレ学童児」として預かってくれるところもあります。
卒園した保育園も3月31日までは通うことができるため、どちらに通うかは家庭で決められます。
入所できるのはどんなご家庭?
入所申し込みの人数が多い時は、各家庭の状況を考慮して入所決定されますが、入所が優遇される家庭はどのような状況が多いのでしょうか。
一例ですが、たとえば以下のような状況であると言われています。
- すでにきょうだいが入所している
- ひとり親のご家庭
- 核家族で両親以外に頼れる身内が近くにいないご家庭
- 近隣学童が遠く通うのが困難
- 両親ともフルタイム勤務
施設によっても調整の仕方はさまざまですが、「より保育に欠けている」家庭が優遇されやすいということです。
学童ライフがスタートすると
同じ園のお友だちがいない、知らない人ばかりの新しい環境にお子さまが慣れるか不安なママパパもいらっしゃることでしょう。「お友だちはできるか」「いじめられないか」「指導員はやさしくしてくれるか」など、心配は尽きないのが親心。
しかし多くの場合は取り越し苦労に終わり、あっという間にお友だちができ、楽しそうに過ごす姿がみられるでしょう。なかなか新しい環境に慣れないお子様もいらっしゃいますが、ママパパが心配しすぎるのはNGです。
心配な時こそおおらかに見守り、どうしても心配な時は指導員に聞いてみるのがおすすめです。
失敗しない学童の選び方
学童には公設学童と民間学童があり、それぞれサービス内容や保育時間が異なるとお伝えしましたが、それだけでは判断基準になりません。実際に見学させてもらったり、可能であれば体験入所もおすすめです。
時間
まずは、預かってもらえる時間が家庭のニーズに合っているかを確認しましょう。他の条件がよくても、時間のニーズに合っていなければお子さまを預けることができません。
平日だけではなく、土日祝日、長期休暇などの保育時間も確認しておきましょう。
学校からの距離やルート
小学生のとくに低学年のお子さまにとって、学校からの距離やルートは非常に大切です。
- 学校から近いか
- 危険な道路を通らず行けるか
- 1人帰りの際危険な場所はないか
- 人通りはあるか
などをチェックしましょう。
学童は、送迎がある場合もありますが、基本的にはお子さまが自分で行き来するところ。なるべく学校や自宅から近い方が望ましいです。1年生の最初は保護者さまが迎えに行くこともありますが、途中から1人帰りできるようになります(※学童によります)。
民間か公設か
民間学童か公設学童か、サービス内容や保育時間、保育料などを考慮して選びましょう。
サービスが良くても、保育料が高すぎて支払いの負担が増えるのは本末転倒ですし、立地や保育料が納得できても保育時間が短くて利用しにくくないか、外遊びできる環境かなど、民間や公設それぞれの違いを理解して選ぶようにしましょう。
施設の設備や雰囲気
見学に行った際、みておきたいのが施設の設備や清潔感です。トイレや手洗い場、キッチンなどの水回りが清潔か、バリアフリーか、掃除は行き届いているかなども大事なチェックポイント。
食べる場所、遊ぶ場所がきちんと分けられているか、具合が悪い時に横になれるスペースがあるかなども見ておくとよいでしょう。
また、学童全体の雰囲気も選ぶ時の重要ポイントです。指導員のかたや通っているお子さまたちの雰囲気を見てみましょう。
指導員のかたの様子
指導員のかたがお子さまにどう接しているかもチェックしましょう。指導員のかたがお子さまに慕われているか、声がけの様子などに着目するとよいでしょう。

お子さまの様子
学童に通っているお子さまの様子をみてみましょう。どんな遊びをしているか、各々好きな遊びを楽しめるスペースはあるか、緊張せずリラックスして過ごせているか…などの施設内の様子から、帰宅途中の様子などを見ておくとよいです。
また、高学年のお子さまが低学年のお子さまの関係性にも着目してみましょう。高学年のお子さまが低学年に優しく接していたり、低学年から慕われている様子がみられたら安心です。
口コミを入手!
近所に学童に通っているご家庭があれば、様子を聞いてみてもよいかもしれません。パンフレットや、指導員の話だけではわからない情報を得ることができます。
料金
学童の費用は毎月の固定費になるため、無理なく支払える額にしましょう。民間学童はサービスが手厚い分、公設学童に比べると高額になりがちです。オプション料金も含め検討して決めましょう。
夜間や休日の運営
急な延長保育や土曜・休日保育などに対応をしてくれる学童もあります。夜間や休日のお仕事があるママパパは確認してみるとよいかもしれません。
学童に入れなかったらどうする!?
学童の申し込み方や選び方をお伝えしました。しかし、学童が足りていないのが現状で入所できないお子さまも増えています。よい学童が見つからない時や、入所できなかったときには、ベビーシッターの利用はいかがでしょう。
ベビーシッターのメリット
学童代わりにベビーシッターを頼むと、以下のようなメリットがあります。
- お子さまやご家庭の状況に合わせて保育できる
- 家庭のニーズにきめ細かく対応できる
- 自宅に来てくれる
- 宿題をみてもらえる
- 習い事の送迎もOK
ベビーシッターはかゆいところに手が届く、オーダーメイドの保育が可能です。共働き家庭が抱えがちな「習い事ができない」といった悩みもカバー。

自宅で、民間学童と同等以上のサービスが受けられるため忙しいママパパも安心です。公的学童のような厳しい審査もありません。
ベビーシッターは料金が高めになりがちですが、補助や助成を利用することでカバーできる部分もあります。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

![[ポピンズシッター]poppins sitter](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/production-penguin-web-assets/assets/top_v1_2/logo_smartsitter-e883a774646de00d9dc586599b6c6aea6e96fa1327ab8745010f386c4e0fa6d4.png)