「子育て支援員」になるには?:子どもに関わる仕事・働き方辞典
横森さや

昨今、「子育て支援員」として働く方が増えています。共働きや子育ての多様化により、お子さまの成長・育ちを支える仕事は需要が高まっており、その結果子育て支援員も注目を集めています。
子育て支援員の仕事の内容や就業場所、目指し方などについてまとめました。
子育て支援員とは?
子育て支援員は、2015年の「子ども・子育て支援新制度」の開始により、保育や子育て支援の人材を増やすために作られた新しい資格です。
内閣府、厚生労働省の指導に基づいた資格で、『子ども・子育て支援新制度ハンドブック』には「地域の子育て支援に携われる人材」という位置付けになると記載されています。
子育て支援員の主な役割
子育て支援員の主な役割は、「地域の子育てを支援すること」です。例えば、保育園や小規模保育施設、家庭的保育事業(保育ママ)、学童保育や子育て支援センターなどで働き、地域の子育て支援をすることが主な役割です。
子育て支援員と保育士とのちがい
お子さまに関わり育ちを支える仕事というと「保育士」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。子育て支援員と保育士は資格と働き方が異なります。
保育士は国家資格である「保育士資格」、子育て支援員は各自治体による民間資格になります。民間資格ということもあり、保育士資格に比べると子育て支援員の資格の方が取得しやすく、働き始めるまでのハードルが低いといえます。働き方にもちがいがあり、保育士がカリキュラムをたて主体的に保育を行うのに対して、子育て支援員は保育補助になります。
子どもや保護者を支えるだけでなく、保育士のサポートも子育て支援員の重要なお仕事といえるでしょう。
子育て支援員の仕事内容は?
子育て支援員は、保育士同様幅広い施設で働くことができます。主な仕事内容は保育補助ですが、具体的な業務についてまとめました。
- 保育補助全般
- お子さま見守り
- 授乳や食事の援助
- おむつ交換やトイレの援助
- 午睡等の寝かしつけ
- 園外保育への同行
- 清掃
- おもちゃや保育用品の消毒
これらの仕事を任されることが多いです。
お子さまと関わる業務が中心ですが、お子さまの午睡中などは保育室の清掃や環境整備などを頼まれることもあります。子育て支援員は保育士や正規職員のサポートが主な仕事なので、資格を取得したばかりの未経験の方も働きやすいといえます。
子育て支援員になりたい!目指し方
「子育て支援員になりたい!」と思ったら、まずは資格を取得しましょう。子育て支援員を目指す方に、資格取得の流れを解説します。
子育て支援員の資格を取得するには
資格を取得するまでは、おおまかに以下の流れになります。
- 都道府県・市町村などの自治体に申し込みをする
- 全員共通の科目を受ける基本研修を受講する
- 希望のコースの専門研修を受講する
- 修了証書が発行され、子育て支援員として認定される
研修内容について
子育て支援員になるためには、基本研修と専門研修を受講する必要があります。基本研修は子育て支援員のイロハを学びますが、専門研修では各施設ごとの特徴に応じた内容を学びます。
基本研修
基本研修は子育て支援の基本知識を身につけるためのもので、子育て支援員の役割や、子どもへの関わり方を8科目・80時間で学びます。
科目は以下の通りです。
- 子ども、子育て家庭の現状
- 子ども家庭福祉
- 子どもの発達
- 保育の原理
- 対人援助の価値と倫理
- 子ども虐待と社会的養護
- 子どもの障害
- 総合演習
専門研修
専門研修は、各事業や施設の特徴や専門知識を学びます。
子育て支援員は、保育園から子育て支援センターなど幅広い施設で働くことができるため、自分が働きたい施設に応じて4つのコースから選びます。
- 放課後児童コース
- 社会的擁護コース
- 地域保育コース
- 地域子育て支援コース
子育て支援員の資格を活かせる職業とは?
子育て支援員の資格を取得後はどのような職場で働けるのでしょうか。
保育施設(保育補助)
専門研修の「地域保育コース」を受講すると、保育園や家庭的保育事業などの保育施設で働くことができます。
主に保育士や正規職員の補助的な役割となり、子どもたちと関わります。自発的に行動するというよりは、保育士の指示を仰ぎ、保育補助として一緒にお子さまの食事や排泄援助、寝かしつけや見守り全般を行います。保育室の清掃やおもちゃの消毒など、補助的な作業を頼まれることも多いです。

学童保育の指導員(補助)
専門研修の「放課後児童コース」を受講すると、放課後の学童保育で働くことができます。指導員の補助的な役割として、子どもたちの遊びを見守ったり、宿題のサポートなどを行います。

ベビーシッター
ベビーシッターは、保育士と同じく専門研修の「地域保育コース」を受講すると働きやすいようです。ベビーシッターは資格がなくても働くことができますが、子育て支援員として学んだ子育てにまつわるさまざまな知識を仕事に活かすことができるでしょう。
今、共働き家庭や核家族の増加により、ベビーシッターの需要は高まる一方。即戦力として活躍することができます。

お子さまが好きな方にぴったり
子育て支援員の資格を取得すると、お子さまに関わるお仕事に採用されやすくなります。現代の子育て支援についての理解も深まり、専門研修ではピンポイントの知識を学べるため安心して働くことができます。
また、子育て環境やお子さまについての理解が深まり、自信を持って関われるようになるでしょう。
「お子さまは好きだけど、未経験で働くのは不安…」という方に、子育て支援員のお仕事はぴったりです。
子育て支援員は保育士同様、お子さまの育ちを支える社会的に有意義なお仕事です。関わりたいお子さまの年齢や希望の就労時間により職場を選択することもでき、自分の都合に合わせて働けるのも魅力です。
お子さまに関わる仕事「ベビーシッター」も検討してみよう
子育て支援員は、お子さまが好きな方にぴったりなお仕事だとお伝えしました。
とはいえ子育て支援員は、補助的なお仕事がほとんどなので、物足りないと思う方もいるかもしれません。
その点、保護者さまのご依頼に添いながら主体的にお子さまと関わることができるのがベビーシッターの仕事です。
保育補助や集団保育では叶えにくい、「一人ひとりのお子さまと丁寧にじっくり関わる」ことができるのも嬉しいポイント。
また、ベビーシッターは、自分のライフスタイルに合わせて働ける自由度の高さも魅力です。
- 週1からでも!
- 場所も選べる
- 子育て経験者歓迎!
ポピンズシッターなら週1でも週5でもOK、ライフスタイルに合わせて働けます。
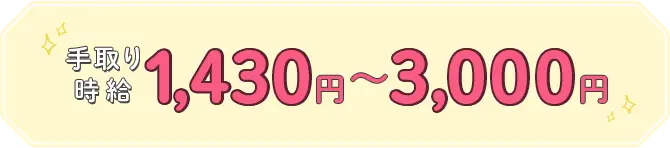
サポートや研修も充実しているだけでなく、多くのシッターが不安に思う依頼者とのトラブルにも対応してくれるため、安心して働けます。
保育士などの子どもに関わる資格を持っているなら、ベビーシッターを検討してみてはいかがでしょうか
まずは無料会員登録!

横森さや
認可保育園で13年働いていた保育士。ベビーシッター、家事代行経験もあり。2児の母でワーママとして頑張るライター。
![[ポピンズシッター]poppins sitter](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/production-penguin-web-assets/assets/top_v1_2/logo_smartsitter-e883a774646de00d9dc586599b6c6aea6e96fa1327ab8745010f386c4e0fa6d4.png)




